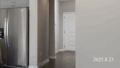まったく。うっかりした。
学校に戻るともう誰もいなかった。ほんとうに誰ひとりとしていなかった。明日から春休みだから当たり前なんだけど、こんなに静かだと気味が悪い。
僕は自分の下駄箱に急いだ。持って帰らないといけないうわばきを置いてきてしまったのだ。
――あった。
空っぽの下駄箱に一足だけ。ほかに忘れた人はいないようだ。
ランドセルを下して、うわばき袋を取り出して、ふと気がついた。
「この下駄箱とも最後なんだな…」
次に学校に来るとき僕は六年生になっている。まだ何組になるかも、担任は誰かも、誰とクラスメイトになるかもわからない。だけど間違いなく僕は六年生になって、六年生の教室で過ごし、六年生の授業を受ける。そして、もちろん六年生の下駄箱を使う。
僕は一列向こうの六年生用の下駄箱を見に行った。
もちろん空っぽだった。手書きの出席番号シールもすべてはがされている。砂粒ひとつない下駄箱は完全に無個性で、ただの四角の連続でしかなかった。それでも僕はちょっとの間、下駄箱を眺めて過ごした。この中のどれかが自分のになるんだな、使いやすい高さのだといいな、なんて考えながら。
自分の下駄箱に戻ろうとしたとき、気がついた。さらに奥にもう一列、下駄箱がある。
どうやら勘違いしていたらしく、向こうが六年生用、さっきまで見ていたのが五年生用だったみたいだ。
うん……? でも、それっておかしくないか。
僕は自分の荷物の置いてある、今日まで使ってきた下駄箱に戻った。それだとここは四年生用ということになる。
僕は自分の下駄箱を見た。確かにここをずっと使ってきたはずだった。出席番号の「16」のシールもないし、周りの靴もなくて、いまいち自信が持てない。だけど、ここにだけうわばきが残されている。ということは、やっぱりここは僕ので間違いない。
僕はこの一年間、気づかずに四年生用の下駄箱を使い続けたのか?
そんなことがありえるのか。
一年間もあって、たったの一回も気づくタイミングがなかったというのか。
というか、本来ここを使うはずの四年生は?
僕は目を閉じて、思い出そうとした。――校舎に入る毎朝の情景を。――一日を終えて帰路につく風景を。今日の今日まで何度も繰り返してきた日常のひとコマだ。だのに、どういうわけか思い出せなかった。
仮に僕がぼんやりしていたとしても、周りの人に声をかけられないのは変だ。だって、他人の下駄箱を私物化することが許されるはずがない。普通の時間に来て、普通の時間に帰るから、どう考えても人に見られているはずなんだけど。
いつの間にか辺りは暗くなっていた。まだお昼過ぎだから、雲が出てきただけだろう。わかってはいても不気味だった。
きっと疲れてるんだ。さっさと帰って家で休もう。
僕はうわばきを下駄箱から出した。
つま先には油性ペンで「ワタナベ」と書いてある。
「ワタナベ……」
その筆跡は明らかに僕のものだ。
そうだ。漢字で書くとつぶれてしまうから、カタカナにしたんだ。
確かに覚えている。覚えているけど……。
「ワタナベって誰……?」
今ここに誰かがいれば、答えが得られたかもしれない。
しかし、春休みをひかえた学校は静かだった。
その声は誰にも届くことなく消えた。
浅瀬にて溺れる(1353字)